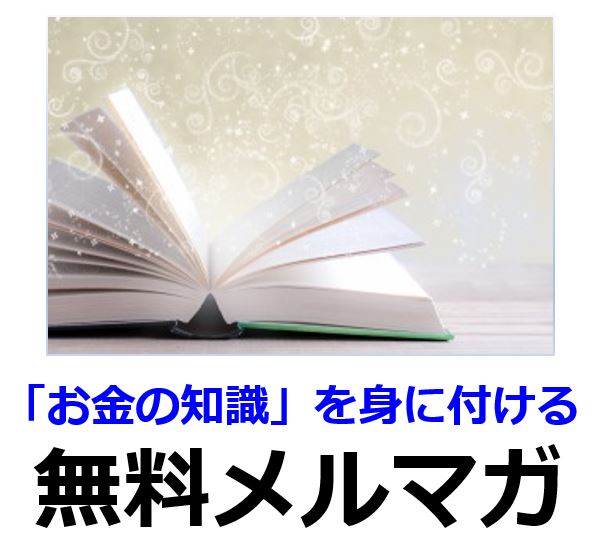「投資詐欺」に遭わないための4つのポイント
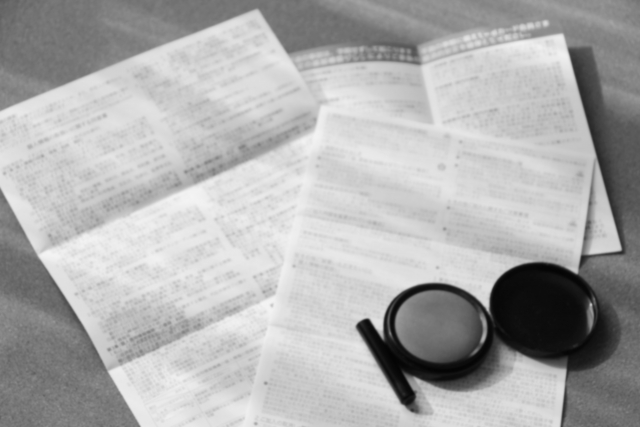
資産運用をしていると、「投資詐欺」の案件を紹介されることがあります。投資詐欺に遭うと数十万〜数百万円もの資金を失ってしまうため、このような案件はなんとしても避けなければいけません。
実際に日本には数多くの投資詐欺案件があります。私自身も投資詐欺によって300万円以上を失ったことがありますし、私の知人にも投資詐欺の被害者は何人もいます。
資産運用をしている人は「資産を増やしたい」という気持ちが強いため、どうしても投資詐欺に遭遇する確率が高くなってしまうのです。
それでは、いったいどのようなことに注意すれば、投資詐欺を見抜くことができるのでしょうか?
今回は「投資詐欺に遭わないための4つのポイント」について解説していきます。当たり前のように思うかもしれませんが、投資をしているときは意外と気づかないので、今回紹介するポイントを心に留めておくようにしてください。
もくじ
1、投資詐欺に遭っても気付かない
2、「投資詐欺」に遭わないための4つのポイント
3、まとめ
投資詐欺に遭っても気付かない
投資詐欺案件は非常に巧妙に作られています。当たり前ですが、顧客に詐欺と見抜かれるようでは、その案件を作る意味がないからです。そのため、基本的には投資詐欺に遭っても気付きません。
詐欺案件を紹介してくる人は、顧客の心理を巧妙に操作し、「確実に儲かりそう」と思い込ませてきます。実態のない資金運用の仕組みをいかにも本当であるように話したり、有名人が投資していることを伝えたりして、顧客を少しずつ信用させてくるのです。
ただ、どれだけ儲かりそうに思えても、有名人が投資していても、一度立ち止まってその案件を見直すようにしてください。詐欺案件は多額の資金を集めるために作られたものなので、理論から仕組みまで「うまくできている」ということを覚えておきましょう。
「投資詐欺」に遭わないための4つのポイント
それでは次に、「投資詐欺に遭わないためのポイント」を紹介していきます。具体的には以下の4点に気を付ければ、ほとんどの投資詐欺を避けることができます。
1、 金融機関と契約する
資産運用では銀行や保険会社、証券会社などの「金融機関」と契約することが大前提になります。金融機関と契約すれば、詐欺に遭うことはありません。また、金融機関であれば国内だけでなく、海外の金融機関を選んでも構いません。
ただ、金融機関から金融商品を購入するときに、一つだけ注意しなければならないことがあります。
それは、金融機関は「必ずしも顧客にとってベストな金融商品を提案してくるわけではない」ということです。
銀行や保険会社、証券会社などの金融機関には「売りたい商品」というのがあります。そして、銀行員や証券マンはその商品を売るための「営業マン」です。
彼らが詐欺案件を勧めてくることはありませんが、顧客にとってベストな金融商品を提案してくれるわけでもありません。実際には良い金融商品を勧められるケースは少ないといってよいでしょう。
金融機関の営業マンのいうことを鵜呑みにするのではなく、自分できちんと下調べをして購入する金融商品を決めるようにしてください。
2、 高利回り商品は詐欺の可能性が高い
投資において、リターンの大きさとリスクの大きさは基本的に比例します。利回りが高い金融商品ほど、損失を出してしまう可能性も高くなるのです。
そして、あまりにも利回りが高い金融商品は、投資詐欺であることが多いです。年利が50%や60%もあるような案件はほぼ間違いなく詐欺なので、手を出さないようにしてください。世界一の投資家であるウォーレン・バフェットでさえ、過去の平均利回りは年間22%程度です。
ちなみに私は、資産運用を始めた頃に年利60%の金融商品に500万円を投資していたことがあります。はじめは順調にお金が入ってきていましたが、あるときを境に急に振り込みが止まり、ついにはその案件が破綻したという連絡が入ったのです。
破綻するまでに200万円近くのお金が入りましたが、投資額には遠く及びません。実質的な損失額は300万円を超えてしまったのです。
このように、高利回りの金融商品は詐欺の可能性があることを覚えておきましょう。
ただ、発展途上国の不動産や価格変動の激しい投資信託のように、詐欺ではない高利回りの金融商品もあります。しかし、これらの金融商品は利益が出るのが一時的であったり、資産価値が大きく下がったりするリスクがとても高いです。
長期的に資産を増やすには、年利8〜10%程度を目安にしてください。これが現実的な資産運用の利回りの上限です。海外の投資信託や定期預金、アメリカの株式などであれば、これに近い利回りを残すことができます。
もちろん、これらの商品にもリスクがないわけではありません。ただ、世界の経済成長や金融機関の投資戦略を考えると、これくらいの利回りを残せる可能性は十分にあります。
3、 金融商品の詳細や投資案件の概要を自分できちんと理解する
投資をしているとテンションが上がることが多いです。資産が増える可能性を感じるので、そのようになるのは当然かもしれません。
ただ、このようなときほど冷静になる必要があります。なぜなら、確実に資産が増えると思い込んだり、自分にとってメリットばかりの契約だと誤解したりすることがあるからです。
金融商品を購入したり投資案件を申し込んだりするときは、詳細や概要を自分できちんと理解しておかなければなりません。相手の言うことだけを鵜呑みにしていてはいけません。利回りや将来的な資産価値を自分で計算できるようになる必要があるのです。
例えば、複利運用で資産が増えていく金融商品であれば、投資額と年利、投資期間から将来的な資産価値を計算できるようにしておいてください。
また、契約書をよく読むことも大切です。契約書には話に聞いていたことと違うことが書かれているケースもあるからです。
場合によっては、弁護士に契約書を見てもらうようにしてください(契約内容をきちんと見てもらうためにも、司法書士ではなく弁護士に依頼することをおすすめします)。
実際に私は契約書の内容に不備を見つけ、弁護士に内容を修正してもらったことがあります。相手との話し合いでその契約は破談となってしまいましたが、安易な契約を交わさなくてよかったと思っています。
4、 謎にいい人は怪しい
最近知り合いになったのに、やけに親切に接してくる人や必要以上に連絡をしてくる人がいます。このような「謎にいい人」は怪しいと思ってください。
ネットワークビジネスをしている人のように積極的にアプローチしてきますが、これはあなたのことを思ってやっているわけではありません。商品や案件を売りたいから話しているにすぎないのです。
そして、このような人は投資詐欺案件を提案してくることがあります。「この人はいい人だ」と思い込んでいると、その案件が詐欺であっても気付きません。相手に左右されるのではなく、商品詳細や案件概要から冷静に判断することが大切です。
以上のように、投資詐欺に遭わないためには、今回紹介した4つのポイントをしっかりと意識してください。絶対とは言い切れませんが、このポイントさえ押さえておけば、あなたの大切な資産を詐欺から守ることができます。
まとめ
・投資詐欺案件は非常に巧妙に作られているため、投資詐欺に遭っていても気付かないことが多い。
・投資詐欺に遭わないためには「金融機関と契約する」、「高利回り商品は詐欺の可能性が高い」、「金融商品の詳細や投資案件の概要を自分できちんと理解する」、「謎にいい人は怪しい」という4つのポイントに気を付けることが重要である。
『お金のガイドブック』: 無料メルマガ
『お金のガイドブック』:Twitter
Twitterでは「最新の経済、金融事情」について発信してます。 ぜひ、フォローをよろしくお願い致します!関連ページ
- 資産運用の必要性:資産運用をすることでお金の知識を身に付ける
- 初心者が知るべき12種類の資産運用:メリット・デメリットを解説!
- 資産運用の3大原則:長期、分散、積み立て
- 「投資」と「投機」の違い
- 資産運用を行うときの心理と注意点:運営者の失敗談も公開
- 資産運用を始めるときのポイント:幅広く情報を集めることを意識する
- 資産運用では「世界経済の成長」に投資することが重要である
- 資産運用では「複利の効果」を利用することが大切である
- 資産運用の基本である「コア・サテライト戦略」
- 値動きの激しい金融商品は「分散」して買うべきである
- 究極の資産形成法である「ドルコスト平均法」
- ドルコスト平均法では「平均取得単価」を考えることが重要である
- 国内投資には「3つのメリット」と「3つのデメリット」がある
- 海外投資には「5つのメリット」と「5つデメリット」がある
- 海外資産を保有する方法と注意点
- 資産を守る方法:預貯金を外貨に換える
- オフショア地域で資産運用をするメリット
- ニュージーランドは安定して資産運用ができる国である
- リーマン・ショックを逆手に取った資産形成法
- ファンド(投資信託)のデメリットとその解消法
- 銀行員が勧めてくる投資信託を買ってはいけない理由
- ETF(上場投資信託)の基礎知識:投資信託や株との違いも解説!
- 債券投資の基礎知識:メリット・デメリット、金利との関係も解説!
- iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)は初心者向きの資産運用である
- FXは危険なギャンブルである
- 宝くじの基礎知識:「還元率」と「当選確率」
- 投資と資産運用の違い:定義、リスク、時間
- 個人投資家と機関投資家の違い:資金力、情報、ノルマ
- Contirbution to world GDP growth (図)
- 長期・積立・分散投資の効果(図)
- ドルコスト平均法(投資信託)
- 値動きの激しい金融商品(図)
- コア・サテライト(図)

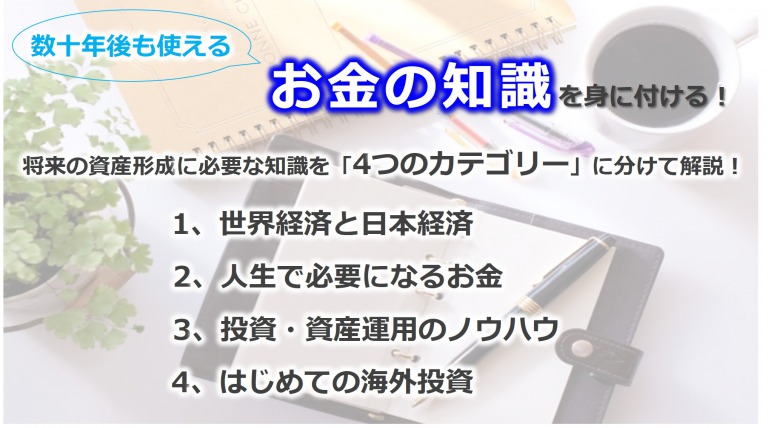
.jpg)